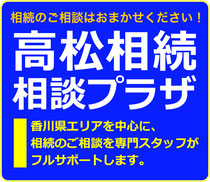相続、遺言|香川・高松の法律相談なら 「法律の病院 福岡司法書士・行政書士合同事務所」へ
相続
人の死亡によりその人の権利義務が別の人に引き継がれるのが相続です。亡くなった人が被相続人、被相続人から権利義務を承継する人が相続人です。相続人が2人以上の場合、相続分や分割方法の問題が発生します。原則、相続人の協議でその問題を解決しますが、協議が調わなければ民法で定められた法定相続分、寄与分、特別受益を基本に家庭裁判所で解決するようになります。また、遺言書が書かれていた場合、遺留分の問題があるとしても遺言書の内容が優先されます。
相続人
相続人には順番があって、第一順位として子と配偶者、子がいない場合(孫がいる場合は孫が子に代襲して相続人となる。これを代襲相続といいます。)は第二順位の親と配偶者、親もいない場合(祖父母もいない)は第三順位の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。なお配偶者は常に相続人となります。兄弟姉妹もいない場合は配偶者だけとなり、配偶者もいない場合は、相続人不存在となり、特別縁故者や国が相続財産を承継することになります。
法定相続分
- 相続人が配偶者と子の場合、配偶者2分の1、子2分の1。
- 相続人が配偶者と父母(祖父母)の場合、配偶者3分の2、親3分の1。
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1。
- 子などが複数いる場合は原則として均等割りとなります。ただし、半血兄弟(父母のどちらか一方を同じくする兄弟)は全血兄弟の2分の1となります。
特別受益
被相続人から生前に他の相続人と比べて特別に贈与を受けた場合をいい、それを相続財産の前渡しと看做(みな)すことでそれぞれの相続人の取り分が変わってきます。
たとえば、長男が商売をするためにその資金として被相続人から500万円の生前贈与を受けた、または自宅を建てるための敷地(500万円相当)の贈与を受けたなどがこれに当たります。
この場合、被相続人が亡くなった時の相続財産に、生前贈与の500万円を加算したものが遺産分割の対象となります。
但し、2019元年7月1日以降、婚姻20年以上の夫婦の一方が他方に居住用の土地建物を生前に贈与していた場合等においては、この特別受益に該当しないこととなりました。
寄与分
被相続人の相続財産に寄与をして本来の相続財産よりも多く相続財産を残すことができた場合のその増えた分をいい、本来の相続分に加算することができます。
たとえば、被相続人が商売をしていたが、長い間病気で仕事ができない状態であったところ、配偶者が一生懸命にその商売をして財産を増やす、または維持してきたことは、通常に配偶者が行う手伝いを超えるものでこれに当たります。
なお、この寄与分が認められるのは相続人に限られていましたが、2019年7月1日以降、相続人以外の親族にも認められるようになり、その者は相続人に対し、寄与分に相当する金銭を請求できるようになりました。

遺言
親族間の争いを避ける完璧な方法はありません。しかしその争いを少なくする方法はいくつかあります。その中で遺言は相続争いを未然に防ぐ、または最小限に抑える効果のあるものです。遺言書を残しておけば原則その遺言書のとおり相続されることになり、親族間の争いはかなり防げるのです。特に相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は相続争いになるケースが多いので必ず遺言書を書いておきましょう。
遺言は貴方ができる最後の法律行為です。貴方の最後の意思が遺族に届くのです。私達の事務所が取り扱った相続でも遺言書があれば相続人間のトラブルを避けられた事例が幾つもあります。私達は遺言書を書くことを強くお薦めします。40歳過ぎれば遺言書を書きましょう。また一度書いた遺言書の内容を変えたいときには新しく遺言書を作成すれば書き換えたことになります。
遺言書の種類
遺言書には普通方式である自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言と特別方式である死亡が迫った人の一般危急時遺言などがあります。最も多い方式が公正証書遺言で次に自筆証書遺言となります。
遺言書の効力はどの方式の遺言書も同じです。複数の遺言書が存在する場合であって、新しい遺言書と古い遺言書とが抵触するときは、その抵触部分については新しい遺言書が有効となります。
自筆証書遺言
一番手軽に作成できるもので、全文を自書し、日付を入れ、自署し、押印することが必要です。
しかし、2019年1月13日以降に作成したものは、財産目録をパソコンで作成したり、通帳をコピーしたものでもその書面に署名押印があれば、全文自書しなくても有効となりました。
自筆証書遺言のメリットは、ほとんど費用を必要としないので何度でも書き直しが可能であり、また内容の秘密保持にも適しています。反対にデメリットは、無効・偽装・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがあり、また家庭裁判所での検認手続きが必要です。
しかし、これも2020年7月10日からは法務局に預けられる制度が施行され、家庭裁判所の検認も不要となるので、これらの問題が解消されます。
公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもとに公証人が遺言書を作成します。公正証書遺言の原本の保存期間は20年間となっていますが、実際は半永久的に公証人役場が保管しています。公正証書遺言では偽造・変造等のおそれはなく、公証人が遺言内容を書くので無効になる心配もなく、それに家庭裁判所での検認の手続きも不要です。また本人が病気などで外出できない場合は、公証人に出張してもらうことができます。ただ公証人の費用が必要となりますが、もっとも安全確実な方法と言えます。なお自筆証書遺言も同じく遺言執行者を遺言内容として記載しておくと、遺言内容を現実化する手続きがスムーズに行われるので忘れずに書いておきましょう。
付言事項
遺言書での法的効力のある記載事項は民法に定められています。これ以外の事項を記載しても法的効力はありませんが、財産の分け方の理由や遺言者の気持ちを書くことによって、より相続間の紛争が回避されることが多いものです。これを付言事項といいます。
注意事項
遺言書には、それを書いた時点での財産について誰に何を相続させるかを記載していますが、現時点での財産の漏れがある場合やその後に増加した財産がある場合には、その記載がない財産について紛争が発生することがあります。ですから、その他一切の財産は誰々に相続させる旨の記載を入れておくのが良いでしょう。

遺産分割
遺言書が存在すれば、その内容通りに相続財産の移行手続きを行い、遺言書がなければ相続人全員で遺産分割の協議をします。遺産分割がスムーズに行われるのであれば何ら問題がないのです。しかし、現実は相続人間の争いとなることが意外に多いものです。相続財産が少ないから争いようがない、兄弟の仲は良いからスムーズに協議が進むというものでもありません。個人の権利意識が強くなる傾向にあり、それぞれが一歩譲って話し合いをする必要があると思います。
分割協議
人の死によって相続人が被相続人の持っていた財産を引き継ぎます。相続人が1人である場合はそのすべてを単独で承継することになりますが、2人以上の相続人がいる場合は相続財産を共有で承継します。このままだと相続人1人1人が自由にその財産を処分することや使用することも不都合なので、相続人全員の合意により遺産を分割することになります。具体的な分割方法には、自宅は長男、農地は二男、ゴルフ会員権は長女というふうに分ける現物分割、相続財産が土地だけで現物分割することができない場合などはその土地を売却換金し、現金で分割するという換価分割による方法です。さらに相続財産が自宅だけで長男が相続し、二男と長女には長男からその代償として金銭を交付する代償分割があります。
配偶者居住権
配偶者居住権とは、相続開始の時に居住していた建物を配偶者以外の相続人が相続した場合において、配偶者が一定の期間(たとえば配偶者の死亡まで)、その建物を無償で居住できる権利です。
この利点は、居住権の評価額のほうが建物の評価額よりも安く算定されるので、配偶者が自宅を相続するよりも居住権を相続したほうがその他の相続財産(預貯金等)を多く相続することができる点にあります。なお、この配偶者居住権は第三者の対抗するためには登記が必要です(2020年4月1日施行)。
分割の調停
相続人全員の一致がみられないときは家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員が間に入って調整に当たってくれ、これによって遺産分割がまとまれば調停調書を作成することになります。調停が成立すると、確定した審判と同一の効力を生じるので、調停調書で不動産や預貯金の名義変更が可能になります。もし調停をしても相続人の意見がまとまらなければ、不調になり審判に移行します。
分割の審判
遺産分割協議がまとまらないからと、いきなり遺産分割の審判の申し立てはできません。まずは遺産分割の調停を経たうえでこの申立てができるのです。申立てをすると相続人の意見を聞いたうえで最終的判断として裁判官が審判を下します。これにより遺産分割が決定されることになります。
遺産分割の問題点
1. 相続人に未成年者がいる場合
片方の親が亡くなった場合、子供の法定代理人はもう一方の親だけになります。しかし遺産分割では親と子の利益が相反するため子の法定代理人になることができないので、家庭裁判所に対して特別代理人の選任申し立てが必要になります。
2. 相続人に認知症の人がいる場合
理解力の程度により手続きは異なりますが、家庭裁判所に成年後見人、保佐人、補助人の選任の申立を行なわなければなりません。
3. 相続人に行方不明の人がいる場合
家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てや失踪宣告の申立が必要になります。

生前贈与
贈与とは、自分の財産を相手方に無償で与え、相手方はそれを受諾する契約です。契約ですから、相続とは法律的には異なるものです。
しかし相続税法では相続税だけでなく、贈与税についても定めています。生前贈与をすることによって相続税を納めることを回避または低く抑えることができるので、贈与税は相続税を補完するために同一の法で規定しているわけです。
1月1日から12月31日の1年間に1人が受けた贈与金額が110万円までは無税、110万円を超える額が増える毎に税率が高くなる累進課税となっています(暦年課税)。
不動産を贈与するとなると少なくとも数百万円以上になるので高率の贈与税が課せられることになります。ただ、次のような税制がありますので上手に利用してください。
相続時精算課税制度
60歳以上の親から20歳以上の子や孫への生前贈与において、2500万円(複数年に渡り利用できる)までは贈与税が係らなく、2500万円を超えた分については20%の贈与税が課せられるものです。ただし相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金のための贈与であれば親の年齢は問いません。
相続発生まで贈与税を猶予され、相続が発生した時に精算(贈与分が相続財産に合計されて相続税として計算)する制度です。
一見すばらしい制度のように見えますがデメリットもあります。一旦この制度を採用すると暦年課税制度に戻ることはできません。暦年課税での毎年110万円の控除が使えなくなります。また暦年課税であれば、亡くなる前3年間の贈与を除き、相続時精算課税制度のように相続時に今までの贈与額が加算されることがありません。
しかし、デメリットを考慮しても一度に大型の贈与をしたい場合などには、この制度を使うメリットがあると思います。
相続時精算課税制度を利用する場合は専門家に相談することをお薦めします。
住宅取得等資金の贈与の特例
2021年まで自己の居住用の住宅取得等資金として直系尊属(父母または祖父母など)から贈与を受けた場合、一定額の控除が認められる制度です。2016年1月1日から2020年3月31日までは700万円(一定の省エネ住宅などは1200万円)※消費税が10%になった場合は2019年4月1日から2020年3月31日までは2500万円(同3000万円)です。
住宅取得等資金の贈与の特例を受けるには相続時精算課税制度と同じく受贈者の年齢が20歳以上の要件が必要ですが、贈与者には年齢制限がありません。
ただし、受贈者の所得金額が2000万円以上だとこの特例は受けられません。
夫婦間の贈与の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に2000万円まで控除できる制度です。 特例を受けるための適用要件は以下のとおりです。
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
- 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

〒760-0080 香川県高松市木太町1582-6
福岡司法書士 行政書士 合同 事務所
電話 087-861-7963 FAX 087-861-7967
E- Mail : info@fukuoka-shihou.com
 *ことでん長尾線 林道駅より徒歩5分
*ことでん長尾線 林道駅より徒歩5分